はじめに
突然ですが、私は幼稚園から高校卒業まで、一度も学校を休んだことがありませんでした。
それにもかかわらず、大学は留年。不登校となりなかなか通学ができず、落ち込んでいた期間が何年もありました。
大学に行けなくなったのは、2年生の前期からです。
特に大きな理由があったわけではありません。いえ、何もなかったわけでもないのですが、
不登校の理由として「ふさわしい」ような理由は特になかったと思います。
(あえてこういう書き方をしています。勿論不登校に理由なんていらないし、ふさわしい理由なんてものもありません)
さて、そんな私でも、冒頭で述べたように、高校卒業までは一種の強迫観念によって皆勤賞を収めていました。
大学で学校に行かないことを不登校と呼ぶ人はあまり多くありません。
不登校、と呼ばれるのはおおむね小中学校――つまり義務教育の間です。
おそらく、教育を受ける権利と教育を受けさせる義務がありながら、
その両方を満たせない、という意味合いで、不登校という言葉が使われるのだと思います。
この真偽のほどは確かではありませんが、
ひとまず当記事では小中学生に限定して、
不登校児の進路を考えていきたいと思います(今回は小学生Ver.です)。
ところで、不登校の児童生徒数について、文科省が調査した、
「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では、
19万6,127人もの児童生徒が不登校となっていることがわかっています。
これはかなり大きな数です。
さらに不登校の数は年々増加傾向にあり、
特に中学生の不登校はかなりの数を占めるという結果が出ています。
これらを踏まえたうえで、今回は小学生で不登校になったときの、
その進路を一緒に考えていきましょう。
小学生で不登校になったら?
まずは小学生の時に不登校となった場合についてみていきます。
不登校の理由は様々ですが、対人関係の問題であったり、家庭環境によるものであったり、
発達障害などの障害が関係していたり、これが一番多い、といった理由はありません。
中には「なんとなく休んだらそのまま行けなくなった」ということも多いのが不登校。
私も、インフルエンザで唯一休んでしまったとき、久しぶりに学校に行くのにとても緊張したのを覚えています。
人間、それまで当たり前のようにやっていたことを急にやらなくなると、
突然当たり前が当たり前じゃなくなり、できなくなってしまうことが少なくありません。
では、小学生で不登校になってしまった場合、どういった進路が考えられるのでしょうか?
フリースクールを活用する
不登校になった子供を、無理やり学校に連れて行くことはあまりオススメできません。
家庭学習がきちんとできれば不登校でも問題ないとよく言われていますが、
共働きであったり、何らかの障害があったりして、家庭学習を行うことが難しい場合、
フリースクールを活用するといった手が考えられます。
フリースクールは、学校に通うことが難しい子どもたちに、学びの場を提供しています。
その種類はいろいろなものがあり、不登校・ひきこもりといったことに特化しているスクールや、
発達障害などの障害を持った児童生徒に対応できる専門家が常駐しているといったスクールもあります。
学校に行きたくても行くことができない、
もしくは子ども自身の意志で学校に行きたくない子どもを持つ親にとって、
第一の選択肢として出てくるのがフリースクールの活用でしょう。
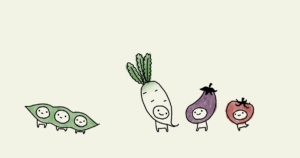
ホームスクーリング(家庭学習)を行う
対人関係に不安がある不登校児の場合、前述のフリースクールに通うというのも困難な場合があります。
最近ではオンラインのフリースクールといったものもコロナの影響で増えてきましたが、
フリースクールでネックなのはそれだけではありません。
小中学校のフリースクールは、そこそこ値段が高かったり、駅から遠い場所に位置していたり、
簡単に通えないのも実情です。
そこで、ホームスクーリング、つまり家庭学習を行うという案が出てきます。
共働きである場合、なかなか子供の様子を確認できないのが難点ですが、
今はホームスクーリングの方法も拡がっています。
例えば、「すらら」というオンライン学習教材では、
一人でも勉強を進められる工夫が多くされているほか、
不登校児でも所定の条件を満たすことで出席日数にカウントしてもらえるというサービスがあります。
家で勉強しても学校の登校日数に数えられる、というのは大変ありがたいですね。
放課後等デイサービスを利用する
発達障害などの障害を持ったお子様の場合、
放課後等デイサービスを利用するといった手も考えられます。
放課後等デイサービスは、障害のある児童が、
学校が終わる時間(15時ごろ)から夕飯前(18時ごろ)まで通うことが出来る施設です。
障害のある子どもたちが放課後過ごせる居場所を作ることで、
お仕事をしているご家庭などのサポートに寄与することを目的としています。
指定の申請等が必要となってきますが、最初から障害児を対象としているため、
それぞれに合ったサポートを受けることができると期待できます。
放課後等デイサービスの月額費用は、福祉サービスのため原則1割負担となるのも嬉しいポイントです。
小学生で不登校になった後の進路について
小学何年生の時に不登校になるかによっても変わってきますが、
新学期がはじまるごとに、そして学年が上がるごとに、登校できることもあります。
しかしながら、夏休み明けにやっと学校に行けたとしても、
体力が格段に落ちているせいで結局不登校になってしまうといったケースもあります。
いよいよ卒業が近づいている、そんな時に不登校の我が子を見るとどうしても保護者の方は焦ってしまうことでしょう。
小学校の次は中学校です。不登校のまま中学校に行けるのか?――そんな不安はなかなか拭い去れません。
その時、考えておきたいのが中学校、さらにはその先まで見据えた進路です。
不登校のまま中学に入る前に考えておきたいこと
不登校になると、もう勉強についていけないのではないか、
中学校に入っても全然勉強が分からずまた不登校になるのではないか、
そういった心配がまず先にされるかもしれません。
しかしながら、最初に心配しておきたいのは「体力」だと私は考えています。
というのも、小学校というのは、結構体力をつける場所です。
まず通学。電車通学やバス通学の場合もありますが、徒歩通学や、電車+徒歩通学など、
通学に当たっては必ず歩くという動作があります。
そして高学年になれば教室移動も多くなり、階段を上り下りすることも多いでしょう。
さらには体育といった体を動かす授業もあります。
不登校になると、これらのほとんどができなくなってしまいます。
だからこそ、不登校の時には勉強だけでなく、
というかむしろ、勉強よりも、運動をさせるようにしておきましょう。
最近はリングフィットアドベンチャーといった、ゲームで楽しめる運動もあります。
毎日ほんの少しでも運動をすることで体力がつき、
なんとか学校に通学できる体力が身につきます。
学校に通学するというのはそれだけで疲れるものです。
その体力を今からでもいいので付けられるよう頑張ってみてください。
(とはいえ、不登校児本人の意思をまずは尊重しましょう)
中学でも不登校になる可能性を考えておく
前向きな記事でなくてすみません。
小学生で長らく不登校だった場合、中学校からいきなり皆勤賞!といったことはまず無理に等しいといえます。
そうでなくても、先述した「体力」の問題や、勉強面での問題、そして対人スキルーー、
中学校ではこれらが格段に難しくなってしまうため、
小学校で不登校だった子供が中学校ではうまくいく、というのは数少ない例だといえます。
それならば、中学校になっても不登校だった場合にどうすればいいか、
先に対策を考えておくのが良い方法でしょう。
当サイトでも中学校で不登校だった場合の進路について、
また記事にさせていただきますので、ご確認ください( *´艸`)
おわりに
ホームスクーリングがまだ浸透していない日本にとって、
不登校というのは不安要素ばかりであり、当事者も、そのご家族も焦燥感などに駆られがちです。
ただ、不登校になったから人生が終わる、なんてことはありません。
確かにレールの上から外れてしまったかもしれませんが、
レールなんてくそくらえです(笑)
これは、私がレールの上をびっしり歩いてきて、そこから急に落ちて、
紆余曲折を経てなんとか違う道を歩けているから言えることかもしれません。
当記事は終始暗い結末だったかもしれませんが、
私は不登校になったからといって人生に絶望する必要はないと思っています。
確かに日本における社会構造は不登校に優しくありません。
でも、10年、20年も経てば不登校時代の話をすることなんてほとんどありません。
未来は未来を生きています。
苦しい今をどうにか生きていく方法を、当事者、ご家族、先生方、地域住民、民間団体……、
いろいろな人たちで模索してください。
不登校のあなたへ。私はあなたのことを応援しています。
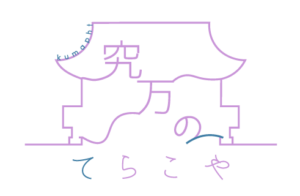





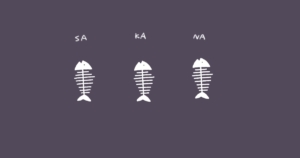







コメント