はじめに
「学校の教室内で先生に指名されると、一言も発せられなかった」
「職場の会議や取引先の人と向き合うと、全く喋れなくなってしまった」
「緊張を強いられる場面になると、全身が固まってしまう」
私たちの身近な人や、自分自身にも当てはまるかもしれないこれらの症状は、
場面緘黙(かんもく)・緘動(かんどう)が原因であると考えられています。

これらは精神疾患とされる症状のひとつであり、子どもの頃に発症するケースが多く、
一昔前は性格上の問題とみなされ、辛い思いを抱えた人たちが少なくないとされています。
ここでは場面緘黙・緘動に関する基礎知識と、
この症状を持つ人たちにまつわる支援や工夫についてご紹介します。
場面緘黙とは
「緘黙(かんもく)」は当事者の症状によって、以下の2つに分類されます。
全緘黙=すべての生活場面において、話すことができない。
場面緘黙(選択性緘黙)=特定の状況下に置かれた時にのみ、話すことができなくなる。
▼ここがポイント
場面緘黙の場合、家庭内などリラックスできる場所では普通に会話できる一方で、
家族以外の人とは話せない特徴がみられます。
一歩家の外に出た途端無口になってしまう症状から、
対人関係に大きな緊張感を覚えてしまうことが、原因のひとつであると考えられています。
★原因が性格によるものとの誤解
場面緘黙は特定の場面でのみ話せない症状が生じるため、
「わざと話そうとしない」など、性格的な問題であると誤解される場合があります。
しかしながらこの解釈は間違いであり、
場面緘黙の症状を持つ人の場合、
どれだけ頑張っても話すことができません。
自ら発言する場面を第三者に見聞きされることに対し、
大きな不安感や恐怖感がぬぐえず、
「話がしたくても声が出せない」「意見を伝えたくても言葉にできない」
など、当事者の困りごとも大きいとされています。
★発症メカニズムは研究段階
場面緘黙の原因やメカニズムに関しては、現時点ではまだしっかりと判明していません。
まだ研究段階ですが、緊張しやすい・不安を覚えやすいなどの要因に、
心理的・社会的・文化的要因が複合的に影響することで、
発症につながるのではないか、と考えられています。
次に子どもの時期に発症する比率が高い理由として、以下の理由が挙げられます。
- 入園・入学による生活環境の変化
- 転居その他による本人を取り巻く家庭外環境の変化
- いじめを受けたことによる精神的圧迫
こういった、不安感が急激に高まったことが引き金となり、
発症してしまうケースが多いとされています。
また稀なケースですが、成人後に場面緘黙が発症する事例も報告されています。
これは子どもの頃からの症状が見過ごされてしまい、
成人後も症状が持続していたために、
発見されるといったことが多く報告されています。
勿論、子どもの頃には全然平気だったのにもかかわらず、
仕事のストレスなどで発症する事例もありますが、
こちらは適応障害や不安障害の診断が下ることが多い印象です。

成人後に場面緘黙が発覚するケースとしては、
- 上司や同僚との意思疎通が上手にできない
- 会議の席で発言できない
こういった、職場などで業務に支障が生じることから、
ようやく周囲の人に気づいてもらえることが多いようです。
場面緘黙の症状
特定の状況下に置かれた時にのみ話せなくなる場面緘黙は、
選択性緘黙とも呼ばれ、以下のような症状が見られます。
また生活環境が異なる子どもと大人では、症状に複数の相違点が確認できます。
★小・中・高校生に見られる症状
家庭とは違い、さまざまな緊張や不安を覚える場面が避けられない学校という空間は、
場面緘黙が生じやすい環境と考えられます。
具体的には以下のような症状が挙げられます。
- 先生に指名されても発言できない
- 教科書の音読ができない
- 授業中に手を挙げられない
- トイレに行きたいと伝えられない
- クラスメートと自然なコミュニケーションができない
- 集団行動時には目立たぬように存在感を消そうとする
- 体育の授業で思い通りに身体を動かせない
★大人に見られる症状
日常生活に加え、職場という大きな緊張感が長時間伴う空間で過ごさねばならないため、
場面緘黙が発症する確率が、自ずと高まります。
具体的には以下のような症状が挙げられます。
- わずかな状況の変化に対しても、不安感や緊張感を覚えてしまう
- 上司や同僚からの問いかけに対し、返事ができない
- 緊張のあまり業務上必要な行動ができず、簡単な動作にも時間を要してしまう
- 指示された業務内容が理解できないにもかかわらず、質問や確認ができない
- 会議の席上で発言できない
- 同僚や取引先関係者との雑談の輪に入ることができない

場面緘動とは
場面緘黙に付随して見られる症状に、場面緘動(かんどう)があります。
これは話せなくなると同時に、自らの体を思うように動かせなくなる症状です。
極度の緊張感と不安感に包まれるため、立ったまま、もしくは座った姿勢のまま、
硬直状態に陥ってしまうケースも見られます。
利用できる支援や相談先
続いて場面緘黙の人が利用できる公的支援と相談先をご紹介します。
▼ここがポイント
場面緘黙は医学的には不安症群に分類されます。
一方で国の基準では「発達障害者支援法」の支援対象に含まれているため、
関連した支援を利用することが可能です。
★場面緘黙の人が利用できる公的支援
・精神障害者保険福祉手帳
一定程度の精神障害状態であることを認定するもので、
各種福祉・公共サービスの利用、障害者雇用枠での就労が可能となります。
・就労移行支援
障害や病気のある人の一般企業への就労を援助するもので、
仕事に必要なスキルや知識の習得から就職活動まで、幅広いサポートが受けられます。
・自立支援医療(精神通院)
精神疾患の治療に要する医療費負担を3割から1割に軽減する制度を活用できます。
★場面緘黙に関する相談先
・発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは各都道府県に設置されており、
発達障害のある人やその関係者を支援する機関です。
・精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは都道府県ごとに設置されており、
電話相談や施設によってはメール相談に対応しているところもあります。
仕事や生活場面でできる工夫
場面緘黙の症状により、仕事や生活場面に支障が生じるケースは少なくありません。
▼ここがポイント
場面緘黙を認識していない周囲の人たちが誤解に及ばぬよう、
自分の症状を整理したうえで、困りごとや必要な対応などを具体的に伝えましょう。
どのような配慮や協力が必要であるかを正しく理解してもらえるよう、
伝え方を工夫することも大切です。
★症状を整理する
まずは、自分の症状が生じる場面を洗い出し、状況を整理するところから始めましょう。
第三者とのコミュニケーションが必要となる場面(場所・相手など)を難易度別に並べ、
- コミュニケーションが可能
- 努力や工夫することでコミュニケーションが可能
- コミュニケーションが困難
の3段階に分けて自己確認します。
ここでいきなり難易度の高い状況でのコミュニケーションに挑んでしまうと、
高過ぎるハードルに屈してしまい、根本的な状況の改善は望めません。
少しずつ上の段階にチャレンジする『スモールステップ』を頭に置いて、
自分なりに実行できそうなところから、いろいろと工夫してみましょう。
★周囲の人への伝え方を工夫する
たとえば、職場で困りごとがある場合、
上司や同僚に以下の内容を伝えるところから、
周囲に理解と協力を求めるとよいでしょう。
- 場面緘黙の症状により、どのような困りごとを抱えているか
- できる仕事とできない仕事
- 必要な配慮や環境調整
口頭で具体的に伝えるのが難しい場合には、次のような方法を用いましょう。
- メールやメッセージなど、文章で伝える。
- 産業医に相談したうえで話し合いに同席してもらい、代わりに説明してもらう
- 支援団体が配布している啓発用書面を用い、周囲の人に理解を求める
緊張感や不安感から言葉が出なくなる場面緘黙だからこそ、
自分だけで解決しようとせず、信頼できる第三者の助けやツールを活用しましょう。
このほか民間の支援団体も活動しています。
たとえば「かんもくネット」では、以下のサービスを提供しています。
- 啓発資料や当事者の体験記などを配信
- 青年・成人用リーフレットを作成から、教育・医療・福祉機関に無料で発送
- 当事者用提示カードの無料ダウンロードが可能
合理的配慮という考え方
自身に必要な配慮や協力について、より正確に伝えるために、
合理的配慮という考え方を知っておくとよいでしょう。
▼ここがポイント
合理的配慮とは障害のある人が障害のない人と平等な社会生活を送るために、
教育や就業の現場で行われる特性や困りごとに応じてなされる、個別の調整です。
ちなみに場面緘黙の症状に対する合理的配慮として、以下のようなものが挙げられます。
- 質問はイエス・ノーで答えられる形で伝えてもらう
- メールやメモなど、文章(筆談)でのやりとりをしてもらう
- 聞き返すことができない場面もあるため、指示にメモを添えてもらう
さらには職場に対し、以下のような配慮を求めてみるのも一案です。
- 音声認識ソフトや会話補助装置などの導入
- 電話応対など声を出すことが前提となる業務から外してもらう
- パーテーションや小部屋などで、1人で落ち着いて仕事ができる環境を確保してもらう
- 産業医、主治医、福祉機関と連携したサポート体制を確立してもらう
まとめ
今回は場面緘黙・緘動に関する基礎知識と、
この症状を持つ人にまつわる支援や工夫についてご紹介してきました。
少しずつできることを増やす「スモールステップ」の考え方が大切です。
ツールを用いる・理解者を増やす、会話以外の方法でコミュニケーションをとるなど、
自分なりの工夫を増やしていけるとよいでしょう。
また場面緘黙の症状がある人は、発達障害者支援法の支援を利用できます。
一人で抱え込まず、今回ご紹介した支援や相談先を活用することも、
視野に入れてみてはいかがでしょうか。
場面緘黙・緘動の症状は人それぞれです。
正しい知識と最新の情報に基づき、ご自身に合った対策や工夫を講じることで、
確実に困りごとを解決していけると良いですね。
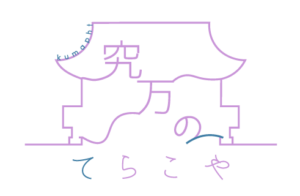





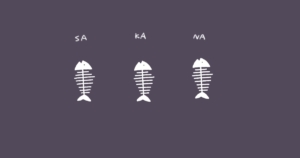







コメント