はじめに

皆さんは感覚過敏や感覚鈍麻といった言葉を聞いたことがあるでしょうか?
“感覚過敏“という言葉自体は少しずつ浸透してきているように思えますが、
おそらく当記事のタイトルを見て、
「他の3パターンは何?」となっていらっしゃる方も多い事でしょう。
さて、私たちが普段意識していない“感覚”についてですが、
これらに著しい偏りがあると、日常生活に支障をきたす恐れがあります。
しかしながら、感覚というのは個々人によって変わるもの。
その困難さはなかなか周囲に理解されず、
当事者にとって大きな負担となっているケースが多く見受けられます。
たとえば次のような特徴がある人が、身近に思い当たりませんか?
- 曇っているのにもかかわらず外を眩しがる
- 身体に触れられることをひどく嫌がる
- いつでもどこでもイヤホンをしている など
もしかするとそういった人たちには、
感覚の偏りが見られるのかもしれません。
私たちが普段何気なくすごしている環境の中にあふれている、
多くの情報や刺激などを、すべて過剰に感じ取っているのかもしれません。
このように仮定すれば、
上記に挙げた特徴的な行動や反応にも理由があることがわかります。
例えば、いつでもどこでもイヤホンをしている人。
彼らは礼儀がなっていないのではなく、
聴覚過敏ゆえに音の刺激を回避しようとしているのかもしれません。
多くの人にとっては何も感じない環境でも、
感覚に偏りがある人の場合、耐えがたい苦痛を覚えるケースが少なくないのです。
感覚の偏り4つのパターン
感覚の偏りは、その傾向により、以下の4つのパターンに分けて整理できます。
客観的に把握すべく、感覚刺激への反応傾向のプロファイリングにおいても、
この区分が使用されています。
① 感覚過敏
刺激に対し過剰に反応するため、
わずかな環境の変化や些細な刺激すらも、
極度に気になる状態を指します。
② 感覚回避
刺激に対する過剰な反応により苦痛を覚えるため、
刺激のある環境を回避する行動に及ぶことを指します。
③ 低登録・感覚純麻
刺激に対する反応が弱いため、
感覚が鈍い=感覚が鈍感であることを指します。
④ 感覚探求
刺激に対して反応が弱いため、
より強い刺激を求める行動に及ぶことを指します。
具体的な事例
感覚の偏りは、体内の全感覚領域で“敏感さ”もしくは“鈍感さ”が生じます。
それぞれに生じる具体的な事例は、以下の通りです。
あくまで一例ではありますが、参考になれば幸いです。
なお
「感覚過敏だから感覚回避を必ず行う」
「感覚探究を行っているということは絶対感覚鈍麻だ」
「感覚過敏だから低登録・鈍麻は見られない」
といったことはありません。
感覚過敏である一方で感覚鈍麻であることも常々で、
そこは両極端の症状ではないということを理解しておいてくださいね。
★視覚
視覚過敏の症状を持たない人は、通常、
自分が注意を向けたい対象物(刺激情報)を無意識に選び、
それだけを捉えることができます。
しかしながら視覚過敏がある場合、
すべての刺激情報を、均一の濃さで受け止めてしまう傾向が見られます。
したがって、原色でカラフルな風景や多くの物が混在する場所では、
それらが一度に襲い掛かるような感覚に陥りストレスを感じやすいといえます。
★聴覚
聴覚過敏と呼ばれる人は多く、
感覚過敏対策グッズの中でも一番ラインナップが充実しているのがこの聴覚についてです。
ノイズキャンセリング機能などを使って、
周囲の環境音から逃れる(=感覚回避)のは、一種の自己防衛といえます。
逆に鈍さを抱えている場合、授業中であるにもかかわらず上の空である場合や、
呼ばれても気づかないといったケースが見られます。
★味覚
多くの人には「美味しい」と感じられるような味でも、
味覚過敏を持つ人たちには、強い不快感を覚えることがあります。
変わった味を好んだり、異なる味が混じることを嫌って全て分けて食べたがったり、
独特の食生活が日常となる人も見られます。
苦みや酸味などを過剰に感じる傾向が見られるため、
自ずと薄味を好み、結果として好き嫌いの差が顕著になりがちです。
対して刺激的な味を好み、調味料や香辛料を過剰に常用するあまり、
健康を害してしまうケースも報告されており、注意が求められます。
★嗅覚
香水などの強い匂いが苦手で、満員電車など人の集まる空間を避ける感覚回避が見られることがあります。
強い匂いでなくても、また一般的には良い香りとされるような匂いであっても、嗅覚過敏者にとってはつらい思いをする原因となることがあります。
頭痛や嘔吐といった身体的症状が出やすいのも嗅覚過敏の特徴です。
★触覚
触覚過敏の場合、皮膚に触れるわずかな刺激でも過剰に感じ取ってしまうことがあります。
触ることが苦手(できない)ものとして、
糊・粘土・スライム(ぬるぬる・べたべた系)、洋服のタグなどがあげられます。
特定の服だけを着たがったり、爪切りや耳かきを嫌がったりするなど、
日常生活においても不快感を回避する反応が見られます。
★痛覚
痛覚に低登録・鈍麻があると、自傷行為をしてしまうことがあります。
自傷行為をする理由にはいろいろなものがありますが、感覚探究が理由の場合、その自傷行為はエスカレートしやすいため、なるべく早めに違う対策を取るのが賢明です。
★温度覚
触覚および痛覚に低登録・鈍麻が見られる場合、温度覚も鈍いことがあります。
ヤケドを負っている、高熱を発症していることなどに気づくことができず、
適切な初期対応が遅れてしまうなど、危険な状況に陥るリスクが心配されます。
★平衡感覚
例えば、平衡感覚が鈍い場合、刺激を求めて頭を振りながら走ったり、まわる遊具などが大好きで離れようとしなかったりします。
逆に敏感であると、頭が傾けられたり身体が傾いたりするのが苦手で、ブランコなどの遊具を避けようとします。
★固有感覚
固有感覚とは、自身が動いた時に感じる、筋肉の張り具合や関節の曲げ伸ばしに対する感覚のことです。
ここにつまずきがある場合、常同行動と呼ばれる同じ行動を繰り返す症状が見られたり、何かにぶつかりにいくといった行動が見られたりします。
感覚過敏などの原因
感覚の偏りについて、その原因に関しては、
まだ研究段階ですが、大きく以下3つの原因に分類できるとされています。
① 脳機能の問題
私たちの脳には、受ける刺激の度合いを適度に調整する機能が備わっています。
しかしながら、何らかの原因で、この機能が正常に機能せず、
たとえば大音量をそのまま受け止めてしまい、過剰に反応してしまうことがあります。
脳神経細胞の過剰興奮に因るてんかん、高卒中、片頭痛が引き金となり、
視覚あるいは聴覚過敏が生じるケースも報告されています。
また自閉スペクトラム症などの発達障害のある人に、
感覚過敏が見られがちであることも知られています。
② 感覚器の問題
目・耳・鼻などの感覚器に原因がある場合も、報告されています。
たとえば耳であれば、突発性難聴、急性低音生涯型感音難聴、
メニエール病などが引き金となり、聴覚過敏となる場合があります。
鼻の場合、後天的に嗅細胞が傷ついたことで、嗅覚情報伝達に不具合が生じ、
嗅覚過敏となることもあります。
③ 心因性その他
緊張時、過労、うつ状態の場面などで、感覚過敏の度合いが高まることがあります。
また認知症の発症が引き金となり、感覚過敏や全身が慢性的に傷む、
線維筋肉証を発症することがあります。
まとめ
感覚過敏という特異性は、ストレスが高まった際により強く生じることがあります。
第三者の目には「自分勝手」「わがまま」と映りがちなため、
性格的に問題があるとの誤解につながりがちです。
まずは、自身の症状をより具体的に周囲の人たちに説明し、
正しく理解してもらえるように努めましょう。
次に、刺激を緩和させる効果が期待されるアイテムを利用するなど、
自身でも色々と工夫する対応も大切です。
また、先に述べた通り、体調が低下した際に感覚過敏が悪化することがあるため、
日頃からの健康管理も無視できません。
感覚過敏や鈍麻があると、
それだけで日常生活は大変ハードルが高いものとなります。
しかしながら、その一部は環境調整や周囲の理解によって、
軽減できる可能性もあるのです。
当事者にとって、より効果的な対処法を確立できるよう私も祈っています。
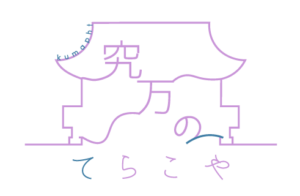





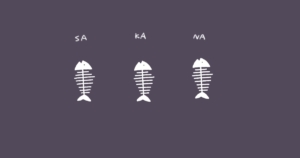







コメント