はじめに
 くま
くま「なんだかこころが壊れていくような気がする……。自分でもよくわからないし、うまく言えないけれど、とにかく助けてほしい……!」
こころの不調は身近な問題ですが、身体のそれとは違い、
自分自身だけでなく、周囲の人にとっても気づきにくい傾向が見られます。
こころの健康回復には、人と人とのつながりが欠かせません。
こころに生じてしまったトラブルを、自分ひとりだけで抱え込まない姿勢が大切です。
今回は、こころの健康状態を意味する「メンタルヘルス」をキーワードに、
世界メンタルヘルスデーに関する基礎知識をご紹介します。
世界メンタルヘルスデーとは
世界メンタルヘルスデーは、メンタルヘルス問題に関する、
- 世間の意識の向上
- 偏見をなくす
- 正しい知識の普及
これらを目的として、
1992年に世界精神保健連盟が10月10日を同日に定めました。
その後、世界保健機関(WHO)も協賛し、正式な国際記念日とされています。
「こころの不調」すなわち、「精神面のトラブル」を抱える人に対する偏見は、
現実問題、世界各地で根強く、本人や周囲がその事実から目を逸らす、
もしくは隠し通そうとする傾向が見られました。
その結果、一般社会から隔離され状況を悪化させてしまうなどのケースも、
数え切れなかったであろうと思われます。
しかしながら、メンタルヘルスにおける問題は、
誰の身にもある日突然生じる可能性がある、こころのトラブルです。
世界メンタルヘルスデーは、
私たちがこの事実を正しく理解しておくことの重要性を、
より多くの人に伝えるうえで、
大いに意義のある記念日といえるでしょう。
メンタルヘルスとは
メンタルヘルスとは、身体ではなく、こころの健康状態を指す言葉です。
例えば、私たちは「身体」の好調もしくは不調を、
次のような感覚で自己確認します。
- 身体が軽い/身体が重い
- 力が湧いてくる/力がでない
- 食欲旺盛/食欲がでない
これらを「こころ」に当てはめてみましょう。
- 気分が軽い/気分が重い
- やる気が湧いてくる/やる気がでない
- 積極的に物事に取り組める/何もかもやりたくない
いかがでしょうか?
誰もが日々の暮らしのなか、
気持ちが沈み、時に激しく落ち込むことがあります。
とはいえ多くの場合は、時間の経過とともに自然と癒され、
元気を取り戻していきます。
しかしながら、元気を取り戻せずに、上記で述べたような、
「マイナスなこころの状態」が続いてしまうと、
こころの健康を崩してしまいかねません。


冒頭でも触れた通り、
こころの不調は周囲の人に気づかれにくく、
当事者自身も気づきにくい問題といえます。
さらには、もし気づけたとしても、当事者と周囲のどちらもが、
「こころの不調」について話題に挙げるのを避けようとしてしまうのが現状です。
誰もがかかりうる「こころの病気」
近年は増加傾向が顕著で、
生涯を通じて5人に1人が発症するとされる「こころの病気」。
毎日の家事がストレスになっていたり、仕事で失敗して落ち込んでしまったり……。
誰でも「こころの病気」の当事者となってしまう可能性があります。
ひとくちに精神疾患といっても、
気分が落ち込んだ状態が続く、不眠に悩まされる、散財してしまう……などなど、
その症状はさまざま、同じ病名でも人それぞれです。
精神疾患に発展する前、
疲れや気分の落ち込みなど、初期症状に気づいた場合、
「もっとしっかりしなければダメだ!」
自分自身を鼓舞して無理をする方もいらっしゃる一方で、
「こんなことくらいでくよくよするなんて、自分は弱い人間だ……」
そう、自らを責めてしまう方もいらっしゃることでしょう。
上記は極端な例ともいえますが、
それぞれ症状を悪化させてしまうリスクが見過ごせません。
こころの異変に気づいたのであれば、
まずは不調に気づくことができた自分自身を、たくさん褒めてあげましょう。
自身をいたわってあげられる休息方法があれば、
そちらを優先してみることは、決して間違った判断ではありません。
それまで無意識のうちに頑張り過ぎた結果、
悲鳴を上げてしまった自分自身の「こころ」に、
「ブレイクタイム(=休憩時間)」をプレゼントしてあげましょう♪
信頼できる相手に、自身の気持ちを吐き出してみるのも一つの手。
身近な人に打ち明けづらい、
相談できそうな人が周囲に見当たらない場合には、
こころの相談窓口などにコンタクトを取ってみるのも良いでしょう。
電話・LINE相談窓口はなかなか繋がらないことも多いですが、
試す価値はあるといえます。
不安や辛い気持ちを言葉にすることで、
こころの負担を軽減する初期対応が大切です。


そしてもし、あなたの周囲に、
こころの不調を感じていそうな人がいたのであれば、
まずはその事実に、そっと気づいて見守ってみましょう。
ここでひとつ注意すべき点があります。
その場でいきなり助けの手を差し伸べるような言動に及ぶことは、
必ずしも相手にとって、喜ばしい対応であるとは限りません。
その人の状態を冷静に見極め、声掛けが必要だと判断できたのであれば、
相手のこころに踏み込み過ぎない距離感で、そっと寄り添ってあげましょう。
もちろん、これはとても難しいことです。
しかしながら、声をかけないよりは、見て見ぬふりをしないよりは、
きっと声をかけたほうが、当事者、周囲どちらにとっても良いはずです。
結果ばかりに着目せず、声をかけられた自身の経過も褒めてあげてくださいね。
シルバーリボン運動とは
話が少し脱線しましたが、
世界メンタルヘルスデーと切り離せない取り組みのひとつを紹介します。
それは、シルバーリボン運動です。
当初は統合失調症への理解を求める取り組みとして、
1993年に米国カリフォルニア州で始まりました。
どんよりとした雲の隙間から射す太陽光が銀色に輝き、
希望の光のようであることから、
「シルバー」がシンボルカラーに決まりました。
その取り組みは年々発展を続け、
現在では以下を目的に、世界各国で展開されています。
- 脳や心に起因する疾患(障害)およびメンタルヘルスへの理解の促進
- これらを抱える当事者やその家族が前向きに生活できる社会の実現
ちなみに日本では、
2002年に福島県浜通り地方(樽葉町)で始まり、
現在はNPO法人シルバーリボンジャパンが、
毎年の世界メンタルヘルスデーに合わせ、
以下のような普及啓発イベントを実施しています。
★世界メンタルヘルスデーJAPAN 2022
「世界メンタルヘルスデーJAPAN 2022」では、
著名人やピアサポーターなどが、
メンタルヘルスについてわかりやすく語ります!
ちなみに今回のイベントの概要は、以下の通りです。
第1部:アスリートなどによる対談(約45分)
10月10日(月・祝)午前10時~ YouTube配信開始予定
トップアスリートの話を聞きながら、
誰にでも起こりうるメンタルヘルスの問題について、一緒に考えます。
第2部:ピアサポーターなどによる対談(約45分)
10月10日(月・祝)午前10時~ YouTube配信開始予定
総合失調症やうつ病などの精神疾患を正しく知り、
向き合うことがなぜ必要であるかを、体験談を交えて一緒に考えます。
※ピアサポートとは、一般に同じ課題や環境を体験する人が、
それぞれの体験から来る感情を共有することで、
専門職による支援では得がたい安心感や自己肯定感を得られることを指します。
まとめ
世界メンタルヘルスデーは、
こころの健康維持に欠かすことのできない、
「人と人とのつながり」を大切にしたイベントです。
「つながる、どこでも、だれにでも」をテーマに、
こころを支える輪を築くイベントの成功を目指しています。
また、メンタルヘルスに関する課題は、
その程度にかかわらず、当事者や関係者だけで根本的な改善、
もしくは解決に至れるようなものではありません。
自治体を中心とする地域精神保健、医療、福祉の一体的な推進にくわえ、
「思いやり」や、「他者を理解しようとする気持ち」など、
この地に生きる人々すべての意識改革が必要です。
世の中全体を見据えた、「こころの健康」に関する取り組みは、
まだまだ始まったばかりだといえます。
まずは私たちひとりひとりが、
自分のために、そして大切な人のために、
無理なく確実にできることから実行に移していきましょう!
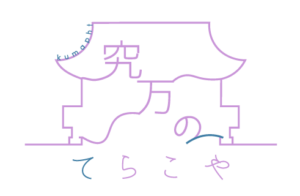





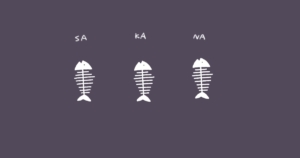






コメント