はじめに
発達障害のある学生の支援は、年々重要性を増しており、
各大学で「合理的配慮」がキーワードとなっています。
ここでは合理的配慮についての解説と、現在各地の大学で実施されている、
合理的配慮の事例をご紹介します。
大学に求められる「合理的配慮」とは?
合理的配慮とは、
障害のあるなしにかかわらず、
全ての人が平等な教育などを受けられるように、
さまざまな場面で発生する困難を取り除くための個別の配慮を指しています。
ひとくちに合理的配慮といっても、
対象者が直面している困難や周囲の環境に応じて、
必要となってくる配慮は異なるため、各々に合わせた対応が必要です。
大学内での「合理的配慮」
合理的配慮は、本人の意志の表明に対して行われる支援です。
大学側には、学生からの意思の表明を受けた時点で、
速やかに支援できる体制構築が求められます。
一方で、対象となる学生の中には、
自身の障害に気づいていなかったり、
障害を受け入れること(=障害受容)ができていなかったり、
障害を自覚していても支援を受けられることを知らなかったり、
……といったケースが、多く見受けられています。
 くま
くまどうしても単位が取れないけれどきっと努力が足りないんだ……



板書が間に合わないけれど写真禁止って言われているから
どうしようもなくて困っている……
このような状態に陥ってしまう学生は数多く存在しており、
相談窓口開設から学生への周知など、大学側の体制整備が重要です。
また、合理的配慮については、
大学側の過度な負担になりすぎないことも要件となります。
障害のある学生に対し、より完璧な合理的配慮を実施するあまり、
他の学生への影響が大きくなり過ぎては本末転倒です。
支援を求める学生の状況に応じて、
個別対応する、代替手段を考えるなど、柔軟な対応が求められます。
大学における「合理的配慮」事例集
では、具体的な「合理的配慮」の事例集について見ていきましょう。
なお、こちらの合理的配慮事例集は、
筆者・究万(くま)が大学で卒業論文を書く際に参照させていただいた、
日本学生支援機構による合理的配慮の事例集(PDF)をもとにしております。
予めご了承くださいませ。
合理的配慮・事例A
文章の読み書きに時間を要してしまうため、
黒板に書かれた内容を授業時間内に書き写すことができない。
デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末での黒板撮影を許可した。
合理的配慮・事例B
教員の話から想像を膨らますことができず、講義内容を理解できない。
絵、写真、図、実物を見せることで、より内容を正確に伝える対応を実践した。
合理的配慮・事例C
マークシート式の筆記試験には対応できるが、
自由記述式の回答用紙に上手に書き込むことができない。
罫線のある回答用紙を使うことで対応した。
合理的配慮・事例D
質問の回答者に指名すると、パニックを起こすことがある。
各教科の担当教員間で情報を共有し、
他の受講生に不自然に映らぬよう、指名対象から外す講義を実践した。
合理的配慮・事例E
周囲のわずかな物音にも過敏に反応してしまい、授業に集中できない。
耳栓やイヤーマッフルの使用を許可し、状況次第では別室に移ってもらうなど、静かな環境の確保に努めた。
合理的配慮・事例F
先の展開を予測することが苦手なため、
未経験の活動に腰が引けてしまい、参加できない。
活動を始める前に、これからの手順や内容を十分に説明することで、不安感を取り除く対応を実践した。
合理的配慮・事例G
時間の見通しが立てられず、別の活動に切り替える際に混乱することがある。
時計、タイマーを用いることで、時間の見通しを本人が確認できる環境を整えた。
合理的配慮・事例H
触覚過敏のため、新しい素材に触れることができない。
また肩を叩かれるなどのコミュニケーションに驚き、パニックを起こしてしまうこともある。
本人が嫌がる対象物に触れることは強要せず、
どうしても必要な場合には、嫌悪感が緩和される方法を検討した。
また直接身体に触れないように注意し、
どうしても必要な場合には声をかけるなど、ショックが軽減されると思われる接し方に配慮した。
合理的配慮・事例I
視覚過敏、特に色覚過敏のため、
絵画の授業中にパニックを起こし、落ち着いて授業が受けられない。
色の薄い用紙や色鉛筆の使用を認めることで対応した。
合理的配慮・事例J
集団で行動する授業に適応できず、1人になってしまう場面が多く見られるが、
本人は授業への参加を希望している。
段階を踏んで無理なく慣れられるよう、集団行動の時間を徐々に増やす配慮をした。
合理的配慮・事例K
物忘れの傾向が顕著なため、宿題の未提出などが繰り返されている。
宿題などの要提出物に関しては、その内容を保護者にも連絡するようにした。
筆者が大学で受けた合理的配慮について
せっかくなので、筆者が実際に大学で受けた合理的配慮についてもご紹介します。
ちなみに、筆者が「合理的配慮」というものを知り、それを大学側にお願いできたのは、
すでに単位をいくつも落とし、留年が決まってしまった後でした……。
なお、2留してしまいましたが、なんとか無事大学を卒業しております。
発達障害の診断は大学2年生のときだったので、
もう少し早く「合理的配慮」という言葉に出会えていたら、と正直思うところはあります。
ちなみに、留年前の大学4年生1回目のときには、
自身が発達障害者であることを一部の教授にお伝えしていましたが、
残念ながら合理的配慮の案内などはなく、こちらから能動的に動かなければ、
その配慮を受けることはできませんでした。
少しずつその体制が変わっていっているといいな、と切に願います。
とはいえ、申請をした後はしっかりと合理的配慮を受けられたので、
以下、その内容を記していきますね!ぜひご参考までに。
睡眠がうまく取れないため、寝坊してしまうことがあり、午前中の授業に遅刻しやすい。
結果として単位を落としてしまうことが多い。
保健室の先生や月に数回いらっしゃる看護師の方と面談をし、
睡眠障害のことや服薬中の薬について伝えた結果、
遅刻した分は違う課題を出すことで単位取得につなげてもらった。
100分の授業時間がとても長く、じっとしているのがきつい。
また、対人恐怖症により、周りの生徒たちの動作・表情が気になってしまい集中できない。
授業中に2回まで、自由に教室の外へ休憩へ行っても良いルールを設けてもらった。
じっとしているのが辛くなってきたときなど、声をかけずに外に出られたので楽な気持ちになれた。
また、授業中における偏光グラスの使用許可をもらった。
所持している偏光グラスの仕様上、相手と目が合わないため、不安軽減につながった。
ビデオを見る授業などが多く、
映像の音が聴覚過敏の筆者には大きすぎて吐き気を催すため、困っていた。
また、課題で動画を見てレポートを書くものがあり、
視覚・聴覚過敏の筆者には苦痛だったため相談した。
授業中におけるノイズキャンセリングイヤホン又はイヤーマフの使用許可をもらった。
それでもつらいときは、教室の外へ出ても良い許可をもらった。
課題については、短い動画の課題のみにしてもらい、
代わりに文章を読むような課題を増やしてもらうことで補ってもらった。
但し、映像主体の授業に関しては、評価を2段階下げるという条件のもと、
動画の課題を半分ほどに減らしてもらった。
※S~ABC、D、X、という評価で、Dはテストを受けたが落単、Xはテストをそもそも受けていないで落単、
実際に単位が取れる評価はCまで、だったため、試験ではS評価レベルのレポートを提出する必要があった。
他にも細かく配慮いただいた合理的配慮はあるのですが、
おおむねこのようなかたちでした。
まとめ
大学で合理的配慮を受けるには、本人の意志の表明が必要ですが、
申し出られずにいる学生も、潜在的に少なくないと思われます。
また支援を行う大学側も、発達障害支援センターとの交流や、
本人の出身校との連携などは、十分とは言えないのが現状です。
合理的配慮を積極的に進めた場合、
より専門的な配慮が求められ、
大学側だけでは対応に限界が生じると予想されます。
より合理的配慮の実績を持つ他の大学や周辺の医療機関、
福祉事業所などとの連携が重要となってくるでしょう。
もし、大学への合理的配慮願いで困っていることがありましたら、
私で良ければご相談に乗りますので、ぜひご連絡ください(お問い合わせ)。
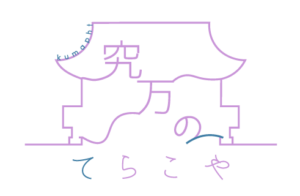

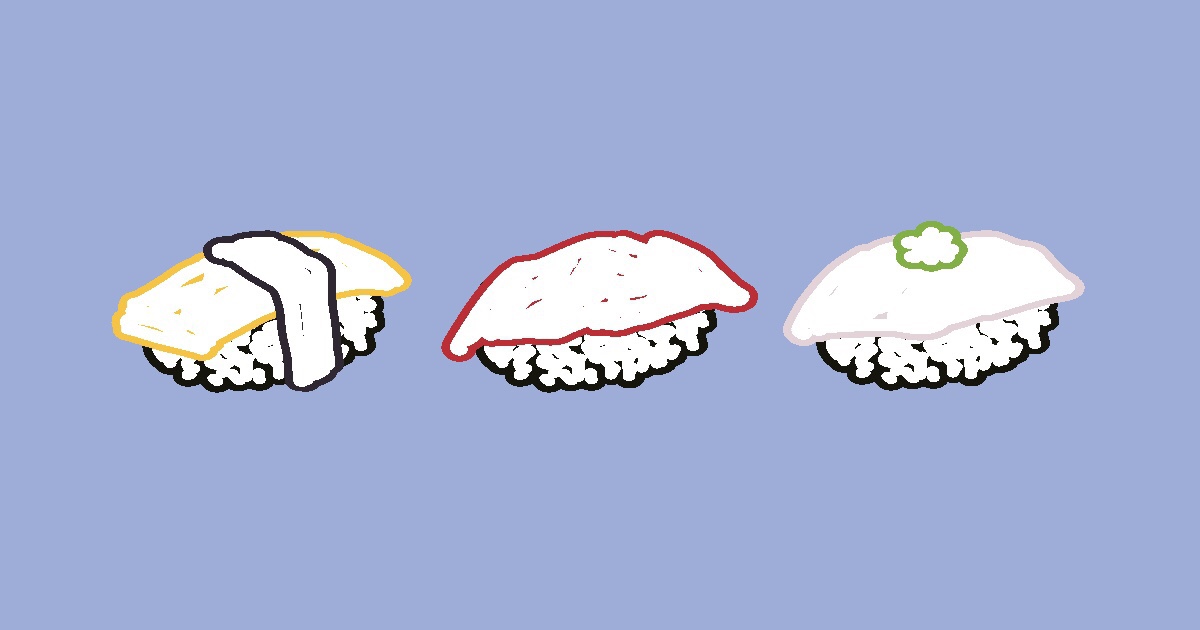
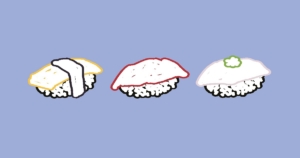


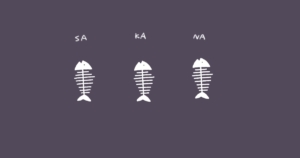







コメント